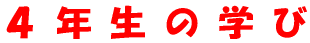
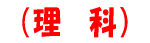
| 「なぜだろう」「もっと知りたいな」ということについて,家庭でもインターネットを使って学びを広げることができますね。 そのためのお手伝いのへやです。 (保護者の皆様へ) 「あたたかくなると」「暑くなると」のいずれも,生き物を扱います。自然環境は厳しい生存競争の場ですが,その事実ととともに,むだに命を人間が奪う必要がないこともお子様に伝えていただければ幸いです。 ▼ あたたかくなると ▼ 電気のはたらき ▼ 暑くなると ▼ 月の動き ▼ 夏の星 ▼ わたしの研究 ▼ 星の動き |
| ▼ あたたかくなると ++++++++++++++++++++++++++++++++++++  冬から春になると,いろいろな生き物に変化が見られるようになってきました。 春先には,こん虫が十分動いたり植物の葉が育ったりしていません。しかし,冬から観察していると,3月ごろに急に虫の種類や数がふえてくることがわかります。 ▼ 冬から春へ,自然はどのようにかわったでしょう 続けて観察できるといいですね。 南小学校では,「観察するんジャー」が活躍します。 ▼ 校庭や野原にどんな動物が見られるようになったでしょう □ 空気の温度(気温)を正しくはかりましょう。 □ 記録カードにひつようなことを記入しましょう。 ・ 観察した年月日,時刻 ・ 天気,空気の温度(気温) ・ 観察したものの名前,場所 ・ 観察したものようすのスケッチ(大きさ,色,形,特ちょう) 特に,数字で表すことができるもの(葉やくきの長さ)はmmなどで表す ・ 調べたこと=(自分が観察してわかったこと) ・ 気づいたこと・感じたこと (記録カードに記入するとともに,デジタルカメラやビデオカメラでようすをとっておくと いいですね) ○「ふしぎ大調査」(NHK) http://www.nhk.or.jp/rika4/ja/frame.html 「2006年度」−「第1回 かえる大発生のなぞ 〜春がやってくる〜」のクリップに, 「ツクシ」「モリアオガエルの産卵」「ヒバリのさえずり」「モンシロチョウの求愛」 「春のぞう木林のようす」「春のぞう木林の変化」「コナラの葉の芽ぶき」 「春のぞう木林のこん虫」「ツバメの巣作りの観察」「春のミツバチの活動」 「ハルジオンにあつまる虫」 などの動画があります。 ○「ふしぎ大調査」(NHK) http://www.nhk.or.jp/rika4/ja/frame.html 「2005年度」−「第2回 お花見大ピンチ 〜春の植物と動物〜」のクリップに, 「空気の温度の調べ方」「春のヘチマ(たねまき・発芽・支柱作り」 「ヘチマのたねまき」「たねのまきかた」「ヘチマの植え替え」 などの動画があります。 ▼ 動物の活動のようすを調べましょう ○「カマキリ日記」(Toto&Bebe さん) http://www.totobebe.nhki.net/doubutu/kamakiri/kamakiritop.htm カマキリの成長のようすを「誕生(たんじょう)」「陽春(ようしゅん)」「たくましく生きる」 「脱皮(だっぴ)」「成長の雨季」「厳しい季節を乗り越えて」 と 1年を通してまとめています。 ▼ 植物の成長のようすを調べましょう □ あたたかくなるにつれて,ヘチマやヒマワリはどのように成長していくでしょう。 家庭では,キュウリやゴーヤ育ててみるのもおもしろいですよ。 実がなれば,野菜サラダやチャンプルーにできます。 ○「ふしぎ大調査」(NHK) http://www.nhk.or.jp/rika4/ja/frame.html 「2005年度」−「第2回 お花見大ピンチ 〜春の植物と動物〜」のクリップに, 「春のヘチマ(たねまき・発芽・支柱作り」「ヘチマのたねまき」「たねのまきかた」 「ヘチマの植え替え」 などの動画があります。 ○「ヘチマを育てよう」(たむたむ さん) http://www2.odn.ne.jp/tam-tam/benkyou/hetima/index.htm 月ごとのヘチマの観察日記があります。 ○「ヘチマを作ってみよう」(全農) http://www.zennoh.or.jp/ZENNOH/TOPICS/kodomo99/Book/hetima/hetima.htm 「ヘチマできれいに!」「作り方」「種類」「歴史」「食べ方」「ヘチマタワシの作り方」 「ヘチマ水の作り方」があります。 ▼ 記録を観察しましょう □ 「継続は力なり」。 記録カードに,植物の成長のようすを続けて記録していきましょう。 (参考図書) ○ 「新編 新しい理科4上」(東京書籍) (もどる) |
| ▼ 電気のはたらき ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 乾電池(かんでんち)と豆電球やモーター,どう線,スイッチを使って車やかい中電とうをつくってみましょう。 また,光電池のはたらきのなぞにせまってみましょう。 ▼自動車をつくって走らせましょう(かい中電とうをつくりましょう) □ 回路が正しいでしょうか。 □ 機械(きかい)部分はただしく動くでしょうか。 □ 回路,電流の向きや大きさについて実験して結果をみちびきましょう。 □ けん流計を正しく使えるようになりましょう。 ○「モーターライズ しよう」(Mabuchi Motor) http://www.mabuchi-motor.co.jp/motorize/ 「モーター博士コース」では,モーターの仕組みについての話があります。 「モーターの選び方」「モーターの力をうまく使うには?」「光電池とモーター」 「工作道具の使い方」などがあります。 ○「乾電池のお話」(FDK) http://www.fdk.co.jp/denchi_club/denchi_story/top_denchit.html 「電池の正しい使い方」「電池の種類」「電池の安全な使い方」などがあります。 ○「ゆかいな電池の森」(松下電池工業) http://panasonic.co.jp/mbi/forest/ 「ゆかいな電池の森」に,「電池はどんなもの」「上手な電池の使い方」 「電池と環境」「電池の実験室」などがあります。 「物知りQandA」には,「電池について」「電池の歴史について」 「電池の使い方について」「環境・リサイクルについて」などがあります。 乾電池をごみとして出す場合,電池の扱いは自治体によってちがいます。各自治体のごみの出し方のポスターやパンフレットをさん考にしましょう。 ▼モーターの回る向きをかえてみましょう □ モーターの回る向きは何をかえるとかわるのでしょうか。 (発展) 豆電球,電子オルゴール,モーターで実験しましょう。 ○「ふしぎ大調査」(NHK) http://www.nhk.or.jp/rika4/ja/frame.html 「2006年度版」−「第3回 あやしいレースカーあらわる」の「クリップ」に, 「電池で動く自動車の作り方」「乾電池で動く自動車が走らないときに」 「乾電池の向きを変えると」「けん流計の使い方」「けん流計の使い方の注意」の 動画があります。 ▼自動車をはやく走らせるくふうをしましょう(豆電球を明るくつくようにしましょう) □ 乾電池を2本使って実験しましょう。 □ 乾電池の組み合わせ方を考えましょう。 □ 乾電池の直列つなぎ,へい列つなぎが確実にできるようにしましょう。 ○「ふしぎ大調査」(NHK) http://www.nhk.or.jp/rika4/ja/frame.html 「2006年度版」−「第3回 あやしいレースカーあらわる」の「クリップ」に, 「乾電池のつなぎ方と自動車の速さ」「直列つなぎ・へい列つなぎ」 「乾電池の数やつなぎ方と電流の強さ」 「乾電池と豆電球のつなぎ方」「乾電池のつなぎ方と豆電球の明るさ」 「直列とへい列の自動車の走り方」「検流計と直列・へい列(モーター)」 「検流計と直列・へい列(豆電球)」の動画があります。 □ 乾電池を正しく使えるようにし,やけどしないようにしましょう。 乾電池とはいうものの,ショートさせると大変。 (直列つなぎ・へい列つなぎ) ○「電池のはたらき」(たむたむ さん) http://www2.odn.ne.jp/tam-tam/benkyou/denti/index.htm 「電池のつなぎかた」「電池のはたらきチェックリスト」があります。 ▼光電池のはたらきを調べましょう □ 発電する電気の量をかえるにはどんな方法があるでしょう。 □ 身の回りのどんなところに光電池が使われているでしょう。 ○「ふしぎ大調査」(NHK) http://www.nhk.or.jp/rika4/ja/frame.html 「2006年度版」−「第4回 しのびよる黒いかげ 〜光電池のはたらき〜」の 「クリップ」に, 「光電池」「光電池と豆電球のつなぎ方」「光電池と乾電池のはたらきの違い」 「光電池で動く自動車」 「光電池に日光をあてると」「光の当て方と光電池のはたらき」 「光の当て方と電流の強さ」「光電池のかたむきとモーター」 「日光をかさねたところの明るさ」 「島や砂漠で使われる光電池」「うちゅうで使われる光電池」「ソーラーカー」 「太陽電池で作られた窓」「身近で使われている光電池」があります。 ○「4年生の実験」(京都府総合教育センター北部研修所) http://www1.kyoto-be.ne.jp/n-center/rika-jikken/4nen-jiken/index.html 『電気のはたらき』に,「かん電池2このつなぎ方」があります。 「かん電池のつなぎ方と電流の強さ」の「ちょっと一工夫」に実験のようすの 動画があります。 「光電池調べ」は,動画による実験風景もあります。 (参考図書) ○ 「新編 新しい理科4上」(東京書籍) (もどる) |
| ▼ 暑くなると ++++++++++++++++++++++++++++++++++++  冬から春になると,いろいろな生き物に変化が見られるようになってきました。 冬から春になると,いろいろな生き物に変化が見られるようになってきました。キュウリやアサガオが花をさかせたり,ミニトマトやナスの実がなったりします。 こん虫も活発に動くようになります。7月に入ると,セミが本格的に鳴き出します。 ▼ 春から夏へ,自然はどのようにかわったでしょう ▼ 校庭や野原の動物は,春のころとどのようにかわったでしょう □ 記録カードにひつようなことを記入しましょう。 「事実」=だれが観察しても同じになるもの 「思ったこと,感じたこと」=個人によってちがいがあるもの をはっきり区別しましょう。 (記録カードに記入するとともに,デジタルカメラやビデオカメラでようすをとっておくと いいですね) □ 「あたたかくなると」のときの記録カードや資料と「暑くなると」の時の記録カードや 資料をくらべましょう。 ○「ふしぎ大調査」(NHK) http://www.nhk.or.jp/rika4/ja/frame.html 「2006年度」−「第6回 ねらわれたコンテスト 〜夏の植物とこん虫〜」のクリップに, 「ヘチマのつる」「ヘチマの成長どこまでのびる?」「夏のヘチマ」 「夏に植物の葉を食べる虫」「夏のハルジオンの花と虫」「夏にさく花とハチ」 「じゅえきに集まるこん虫たち」「夏のぞう木林のじゅえきとこん虫たち」 「アザミの花とこん虫」「夏のカブトムシの活動」「夏のミツバチの活動」 「夏のぞう木林のこん虫」「夏のこん虫のさがし方」「クマゼミの羽化(うか)」 などの動画があります。 ○「生き物の部屋 −テントウムシ 成長編−」(T.Kaze/Family Page Hiroshima) http://homepage3.nifty.com/f-page/kima/ikimono/ikimono3.html テントウムシの幼虫(ようちゅう)−さなぎ−羽化(うか)のようすを月日,静止画, 文でまとめています。 ○「アゲハチョウの観察記録」(仙台市立北六番小学校) http://www2.sendai-c.ed.jp/~kitaroku/k6siryousitu/kannsatu/821.htm#agehatop アゲハチョウの幼虫(ようちゅう)−さなぎ−羽化(うか)のようすを月日,静止画, 文でまとめています。 ○「カマキリ日記」(Toto&Bebe さん) http://www.totobebe.nhki.net/doubutu/kamakiri/kamakiritop.htm カマキリの成長のようすを「誕生(たんじょう)」「陽春(ようしゅん)」「たくましく生きる」 「脱皮(だっぴ)」「成長の雨季」「厳しい季節を乗り越えて」 と 1年を通してまとめがあります。 ○「素材集(動画・静止画)」(top4 さん?) http://nio.no-ip.com/movie/ アゲハチョウの「卵のようす」「ふ化の瞬間」「脱皮の瞬間」「幼虫からさなぎへ」の 動画があります。 QuickTimeが必要です。。 ▼ ヘチマやヒマワリはどのように成長してきたでしょう ○「ヘチマを育てよう」(たむたむ さん) http://www2.odn.ne.jp/tam-tam/benkyou/hetima/index.htm 月ごとのヘチマの観察日記があります。 ○「ヘチマ日記」(スタジオ・デルタ) http://www.bea.hi-ho.ne.jp/delta/sub4-h.htm 5月から12月まで,ヘチマを観察したようすを記録しています。 (ツバメの成長について) ○「ふしぎ大調査」(NHK) http://www.nhk.or.jp/rika4/ja/frame.html 「2006年度」−「第5回 消えたツバメのなぞ 〜ツバメの子育て〜」のクリップに, 「巣を作るツバメ」「ツバメノ巣の作り方」「ツバメノ産卵とひな」 「ツベメのひなにえさ運び」「ツベメの巣立ち」「ツベメの子育ての観察」 「ツベメのえさとりとえさやり」「ツベメのえさのとりかた」「ツバメののき下の子育て」 「東南アジアから日本へ渡るツバメ」 などの動画があります。 (参考図書) ○ 「新編 新しい理科4上」(東京書籍) (もどる) |
| ▼ 月の動き ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ もっともわかりやすく見ることができるわく星,月。 学校ではなかなか観察できないので,家庭で安全に気をつけて観察しましょう。 □ 月の位置(いち)と時間のかんけいを観察しましょう。 (準備物)方位磁針,記録カード ★ 自分の家(しき地内)から見える場合はいいですが,自分の家から少し離れた ところから観察する場合は,おうちの人といっしょに見ましょう。 ★ 行き来には,交通安全にくれぐれも気をつけましょう。 ★ 何かあったら大声でまわりの人に知らせたり,あいているお店の中に逃げて 知らせましょう。 ▼夜空を見上げよう □ 月について知っていることを話し合いましょう。(メモしましょう) ▼月の動きを調べよう □ 事前に月や太陽の動きをたしかめておきましょう。 ○ 観察の仕方,記録の仕方 位置・時刻(じこく) ○ 方位じしんの使い方 ○「アストロアーツ 星空ガイド 月齢(げつれい)カレンダー」((AstroArts) http://www.astroarts.co.jp/cgi-bin/moon-calendar-j 月齢と月の満ち欠け(みちかけ)のようすがカレンダーとともに見ることができます。 ○「各地の月の出・南中・月の入り時刻」(国立天文台) http://www.nao.ac.jp/koyomi/ 「今日のこよみ」では,都道府県庁所在地の月の出・南中・月の入り時刻が わかります。 「各地のこよみ(表引版)」では,月の出・月の入りの時刻が表になっています。 「今日の星空」で主な惑星(わくせい)のようすがわかります。 ○「万能プラネタリウム」(つるちゃん さん) http://homepage2.nifty.com/turupura/java/TuruPla.htm 「つるちゃんのプラネタリウム for Javaアプレット」の1ページ。 月やわく星の位置がわかります。 月の形は変化しないので,月齢カレンダーといっしょに使いましょう。 「年月日時」「観測地」を指定してください。 「図法」は「半球」に変えた方が見やすいです。 「大三角形」の□にチェックマーク(レ)を入れましょう。 太陽が出ているはずの時刻でも空は暗いので,常に時刻はチェックしましょう。 ○「月の呼び名」(eiko matsumura さん) http://www.asahi-net.or.jp/~NW6E-MTMR/moon/name.htm 月齢と月の呼び名を対応して表示しています。 ○「ふしぎ大調査」(NHK) http://www.nhk.or.jp/rika4/ja/frame.html 「2006年度」−「第8回見えない月をさがせ 〜月を観察しよう〜」の 「クリップ」に, 「夕方に見える月」「夕方に見える半月の動き」「満月の動き」 「三日月の動き」「月の形が変わるわけ」などの動画があります。 (発展) 「月」にきょうみがあっって,もっと調べたいという場合は,以下のWebページも見てみましょう。 ○「The Moon Age Calender」(The Moon Age Calender) http://www.moonsystem.to/outline.html 「Details」に,「Moon Map」(月面地図)があります。 ○「デジカメで撮影した月の写真です」(しが さん) http://www.d-b.ne.jp/siga/tentai/getumenn.html 天体望遠鏡で見た月をデジタルカメラでうつした写真があります。 ○「太陽系 月」(宇宙情報センター) http://spaceinfo.jaxa.jp/db/utyu/taiyokei/taiyokei_j/tuki_j.html 「太陽系(たいようけい)のなかのどの位置にあるの?」 「内部の構造(こうぞう)はどのようになっているの?」 「どんな特徴(とくちょう)があるの?」 「どんな環境(かんきょう)の星なの?」などがあります。 ○「フリー百科事典『ウィキペディア』 月」(Wikipedia) 百科事典形式(ひゃっかじてんけいしき)で,月についての説明があります。 ○「RETURN to THE MOON」(科学技術振興機構) http://jvsc.jst.go.jp/universe/luna/index.html 「月をめざして」「アポロ計画から惑星(わくせい)科学へ」 「月のミステリー」の動画があります。 ○「月や金星の形(見え方)はなぜ変わる?」(佐賀県教育センター) http://www.saga-ed.jp/workshop/edq01461/ 「月ってどんな天体?」「月の満ち欠け」「宇宙へ行ってみよう」 「わかったかな?」があります。 ○「月はどのように満ち欠けするのかな?」(学習研究社) http://kids.gakken.co.jp/kagaku/rika/a5-1.htm 月の満ち欠けについて,プレゼンテーション形式で知ることができます。 (参考図書) ○ 「新編 新しい理科4上」(東京書籍) (もどる) |
| ▼ 夏の星 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 夏には,夏に見られる星座(せいざ)があります。 どんな星座があるか,また,有名な星はどんな名前がついていてどの星なのか,じっさいに観察して見つけてみましょう。 ▼夜空を見上げよう 夜空を見上げてみましょう。どんな星座(せいざ)や星が見えますか。 □ さそり座は見つかりましたか。 □ アンタレスは見つかりましたか。 □ はくちょう座は見つかりましたか。 □ デネブは見つかりましたか。 □ こと座は見つかりましたか。 □ ベガは見つかりましたか。 □ わし座は見つかりましたか。 □ アルタイルは見つかりましたか。 □ デネブ・ベガ・アルタイルを結ぶ「夏の大三角」を見つけましたか。 (注意) ○ 必ず,家の人といっしょに見にいきましょう。 ○「万能プラネタリウム」(つるちゃん さん) http://homepage2.nifty.com/turupura/java/TuruPla.htm 「つるちゃんのプラネタリウム for Javaアプレット」の1ページ。 月やわく星の位置がわかります。 月の形は変化しないので,月齢カレンダーといっしょに使いましょう。 「年月日時」「観測地」を指定してください。 「図法」は「半球」に変えた方が見やすいです。 「大三角形」の□にチェックマーク(レ)を入れましょう。 太陽が出ているはずの時刻でも空は暗いので,常に時刻はチェックしましょう。 ○「アストロアーツ 星空ガイド 月齢(げつれい)カレンダー」(AstroArts) http://www.astroarts.co.jp/cgi-bin/moon-calendar-j 月齢と月の満ち欠け(みちかけ)のようすがカレンダーとともに見ることができます。 ○「各地の月の出・南中・月の入り時刻」(国立天文台) http://www.nao.ac.jp/koyomi/ 「今日のこよみ」では,都道府県庁所在地の月の出・南中・月の入り時刻が わかります。 「各地のこよみ(表引版)」では,月の出・月の入りの時刻が表になっています。 「今日の星空」で主な惑星(わくせい)のようすがわかります。 ○「プラネタリウムのホームページリンク」(加藤治 さん) http://www.planetarium.to/ 日本全国各地のプラネタリウムを有する施設へのリンクがあります。 ○「ふしぎ大調査」(NHK) http://www.nhk.or.jp/rika4/ja/frame.html 「2006年度」−「第7回たからのありかは星に聞け 〜夏の空を観察しよう〜」の 「クリップ」に, 「夏の星ざ−さそり座」「夏の星ざ−はくちょうざ」「夏の星ざ−ことざ」 「夏の星ざ−わしざ」「夏の大三角」 「つぎへ」に, 「七夕と天の川」「星の観察の仕方と注意」「ほういじしんの使い方」 「げんこつで高度のはかりかた」の動画があります。 (参考図書) ○ 「新編 新しい理科4上」(東京書籍) (もどる) |
| ▼ わたしの研究 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 夏休み,学校で学習があるときよりはゆったりとすごせますね。 このチャンスに,「自由研究」にチャレンジしてみましょう。 (ポイント) 1 自分が感じた「なぜだろう?」を大切にテーマを決めましょう。 ○ 「こんな考え方があるんだ」とほかの人が思うテーマになるといいですね。 2 夏休みは長いとはいうもののずっとあるわけではありません。 ○ 夏休みをすぎても自由研究をずっと続けていって,もちろんかまいません。 ○ しかし,作品展に出すには「しめきり」があります。 3 数や量などで表せるもの(客観的データ)を記録しましょう。 ○ 「小さかった」ではなくて「mm」で。 4 五感を使いましょう。 ○ 見た感じ(色など),手触り(やわらかい,すべすべしているなど),音,におい, 場合によっては味(安全なものだけですよ!) 5 「おどろき」を大切にしましょう。 ○「感動した!」「わかった!」ことを観察したり実験したりした結果とともに まとめましょう。 (自由研究のすすめ方について) ○「夏休み特集! 理科の自由研究のまとめ方 〜実験のばあい〜」(住友化学) http://www.sumitomo-chem.co.jp/junior/01katei_sub/020jiyu_kadai/index.html レポート用紙にまとめる方法を説明しています。 「まとめに必要なものの準備と仕上げ方」「まとめに必要な項目」があります。 ○「自由研究のてびき」(日本標準) http://www.sumitomo-chem.co.jp/junior/01katei_sub/020jiyu_kadai/index.html 3〜6年まで学年ごとにステップに分けて研究のすすめ方をまとめています。 テーマの見通しチェックができます。 ポスター,本,新聞形式でのまとめ方があります。 (科学作品の例) ○「平成14年度版 第13号科学研究の手引」(つくば市教育委員会) http://www.tsukuba-ibk.ed.jp/online/modules/tinyd5/content/index.php?id=7 科学作品小学校の部の優秀作品が15点あります。 PDF形式。 (そのほかのさんこうになるWebページ) ○「自由研究ガイド」(東京書籍) http://www.tokyo-shoseki.co.jp/2002natu/htm/jiyukenkyu.htm 自由研究のすすめ方の説明があります。 ○「自由研究のページ」(ashitaka さん?) http://www.wombat.zaq.ne.jp/ashitaka/kenkyu/jiyu.html 「ここがポイント」に,自由研究のこつの説明があります。 自由研究に関係する「自由研究のリンク集」もあります。 (どうしてもテーマが思いうかばなかったら) ○「夏休み自由研究プロジェクト2006」(学習研究社) http://kids.gakken.co.jp/jiyuu/ 7月3日公開予定。 「小学1〜6年」「小学1・2年」「小学3・4年」「小学5・6年」に分けて理科に関係する テーマをしょうかいしています。 (参考図書) ○ 「新編 新しい理科4上」(東京書籍) (もどる) |
| ▼ 星の動き ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 夏には,夏に見られる星座(せいざ)があります。 どんな星座があるか,また,有名な星はどんな名前がついていてどの星なのか,じっさいに観察して見つけてみましょう。 ▼星を調べよう 夜空を見上げてみましょう。どんな星座(せいざ)や星が見えますか。 (ふくしゅうです) □ 夏の星座,さそり座・はくちょう座・こと座・わし座をすぐに見つけることが できますか。 □ アンタレス・デネズ・ベガ・アルタイルをすぐに見つけることができますか。 □ 「夏の大三角」をすぐに見つけることができますか。 (新しく見つける星座や星です) □ 北斗七星を見つけることができましたか。 □ カシオペヤ座を見つけることができましたか。 □ 北極星を見つけることができましたか。 (注意) ○ 必ず,家の人といっしょに見にいきましょう。 □ 星座の主な星の明るさや色を記録できましたか。 「万能プラネタリウム」で星座の位置をあらかじめつかみ,星座にならぶ星のようすを知っておきましょう。実際に星座を観察するときに便利です。 ○「万能プラネタリウム」(つるちゃん さん) http://homepage2.nifty.com/turupura/java/TuruPla.htm 「つるちゃんのプラネタリウム for Javaアプレット」の1ページ。 月やわく星の位置がわかります。 月の形は変化しないので,月齢カレンダーといっしょに使いましょう。 「年月日時」「観測地」を指定してください。 「図法」は「半球」に変えた方が見やすいです。 「大三角形」の□にチェックマーク(レ)を入れましょう。 太陽が出ているはずの時刻でも空は暗いので,常に時刻はチェックしましょう。 □ 星座の位置と星のならびかたを調べましょう。 ○ 方位と高度を調べ,記録します。 それとともに,星座の星のならびをスケッチします。 ○ 2時間後に観察した,星座の星のならびをスケッチします。 □ 星も,太陽や月のように動いているか,どのように動いているか確かめましょう。 ○ 動かない星を見つけましょう。 ○ 星座の位置と星のならびかたを調べた結果,どのようなことがわかりましたか。 ○「ふしぎ大調査」(NHK) http://www.nhk.or.jp/rika4/ja/frame.html 「2006年度」−「第7回たからのありかは星に聞け 〜夏の空を観察しよう〜」の 「クリップ」に, 「夏の星ざ−さそり座」「夏の星ざ−はくちょうざ」「夏の星ざ−ことざ」 「夏の星ざ−わしざ」「夏の大三角」 「つぎへ」に, 「七夕と天の川」「星の観察の仕方と注意」「ほういじしんの使い方」 「げんこつで高度のはかりかた」の動画があります。 ▼ うちゅうのひみつをさぐる ○「すばる望遠鏡(ぼうえんきょう)」(国立天文台) http://www.naoj.org/j_index.html 「すばるキッズ」「ギャラリー」などがあります。 ○「ハッブル宇宙望遠鏡がとらえた宇宙の姿(すがた)」(国立天文台) http://th.nao.ac.jp/openhouse/1999/hst/index_hst.htm ハッブル宇宙望遠鏡でさつえいした画像があります。 (参考図書) ○ 「新編 新しい理科4上」(東京書籍) (もどる) |