| 2002-2004年度 学力向上フロンティア事業研究紀要 教科学習の見直しと評価の改善 |
| 6節 補充的な学習と発展的な学習 ▼補充的な学習と指導の工夫 (1) 補充的な学習とは ○ 最低規準の学習内容をマスターできるようにするために,「分からない」 「できない」子どもを「分かる」「できる」状況まで高める学習。 <C評価の子ども対象> ○ 補充的な学習の内容には,知識・理解の補充学習,技能習熟の補充学習, 数学的な考え方の補充学習等が考えられる。 (2) 補充的な学習についての指導の工夫 ○ 繰り返し学習による補充 同一または類似の内容を必要に応じて繰り返し学習する。 ○ 算数的活動による補充 作業的・体験的な活動など算数的活動を繰り返し行うことで,数量や図形 についての感覚を豊かにしたり意味理解を深めたり考える力を高めたりする。 ○ 多面的な学習による補充 同じ内容を別の場面,別の方法などで調べたり確かめたりして学び直す。 ▼発展的な学習と教材 (1) 発展的な学習とは ○ 子どもがそれまでに身に付けてきた基礎的・基本的な内容を基にして,より 広げたり深めたり進めたりする学習。<B・A評価の子ども対象> ○ 発展的な学習には,次の2つの内容がある。 ・ どの子にも触れさせたい内容 ・ 習熟の進んだ子に取り組ませたい内容 ○ 発展的に考える子どもを育てるために次のような力や態度を育てる。 ・ 自ら発展させていこうとする力や態度 ・ ものごとを多面的・柔軟的に考える力や態度 ・ 個々の自然の問いを生かしていく力や態度 (2) 発展的な教材とは 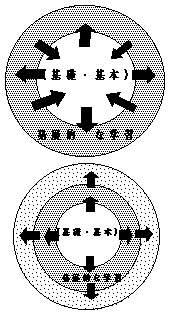 ○ 学習した基礎・基本を深めるための発展的な教材 ○ 学習した基礎・基本を深めるための発展的な教材その単元で学習した知識や技能・考え方を使って, 今までの学習内容から少し拡張した場面で,知識や 技能を使いこなし,基礎・基本のより確実な定着を 図れるもの。一歩先に進めながら元をふり返れるもの。 <B評価の子ども対象> ○ 学習した基礎・基本を広げるための発展的な教材 分かった・できたと思ったことを,その単元で学習 した場面とは別の場面で活用したもの。その単元の 学習内容の次にくる内容への橋渡しにもなるもの。 <A評価の子ども対象> ▼ 補充的な学習・発展的な学習の設定 (1) 1時間の授業の中で行う場合 T・Tでの指導の場合は,1時間の終末に個の到達状況に応じて,補充的な学習や発展的な学習を行う。 習熟度別学習では,1時間の終末に,基礎・基本の習熟が高い子どものコースには基礎・基本の内容を活用する場面を設定する。 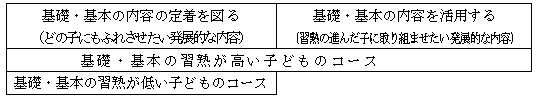 (2) 1単元の中で行う場合 補充的な学習と発展的な学習は,学習の定着度の差が大きくなったときに,次のように,小単元単位で設定する。 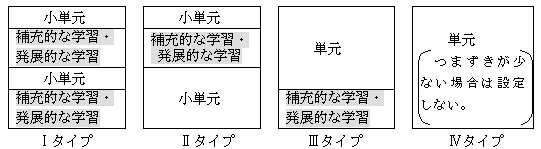 新しい単元の学習を始める際に,その単元を学ぶために必要な既習事項の習熟の程度の違いを解消する補充的な学習を行う場合もある。 ▼コース別学習におけるコース選択 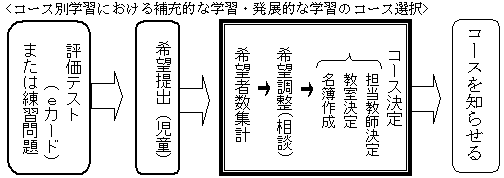 ▼補充的な学習・発展的な学習の評価 補充的な学習の評価では,C評価の子がB評価になったのか,発展的な学習の評価では,B評価の子がA評価になったのかを,それまでに設定していた評価規準に照らし合わせて評価し,その後の学習に意欲的に取り組ませたり,指導に生かしたりする。なお,授業や小単元・単元の終末等で行われる補充的・発展的な学習については,児童のよい点や可能性,進歩の状況等の評価(個人内評価)を重視する。(補充的な学習・発展的な学習の実践例参照) ▼はげみと補充学習の時間の設定 毎週金曜日に「はげみの時間」(1〜3年は5校時,4〜6年は6校時)を設定し,教科指導の補充的な学習や発展的な学習を行っている。 また,はげみの時間に続けて,「補充学習」の時間(1〜3年は6校時,4〜6年は15:40〜16:20)を設定し,個に応じた補充・発展の学習を行い,基礎学力の定着をめざしている。 毎週金曜日に「はげみの時間」(1〜3年は5校時,4〜6年は6校時)を設定し,教科指導の補充的な学習や発展的な学習を行っている。 また,はげみの時間に続けて,「補充学習」の時間(1〜3年は6校時,4〜6年は15:40〜16:20)を設定し,個に応じた補充・発展の学習を行い,基礎学力の定着をめざしている。 |