7節 国語科学習(説明文教材)の見直し
▼国語科の授業でめざすもの
学習指導要領改訂の方針のもと,国語科の目標が以下のように示された。
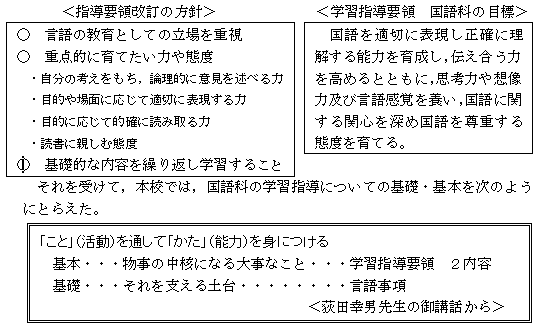
そして,説明的文章の読みを中心に,授業の見直しを図り,単元セット(b,c,eカード)を作成して活用する。
▼具体的指導法の改善
学習目標を達成するためには,単元や授業を構築していく中で,具体的指導法の改善を図ることが重要である。その視点として以下の4点を取り上げる。
○ 子どもの意欲や課題意識を生かしながら目標に迫るための活動
○ 子どもの課題意識をもたせ意欲化を図る単元計画や授業
○ どの子にも目標を達成させるための支援
・少人数指導のあり方
・教具やワークシート・助言などの細かな手だて
○ 読みと表現の関連
▼評価の改善
語科の授業において,「関心・意欲」や「聞くこと」「読むこと」等理解の領域は頭の中でなされるものであり,それ自体は見えにくい学力とも言える。こうした,思考や感覚を伴う,見えにくい学力を評価する方法を開発し,指導に生かしたいと考えた。
(1) 過程の学力
国語科でも算数科と同様にめざす子ども像を具体的に示し,授業の中で求める姿が表出された時,そのよさを賞賛し学び方として位置づけ,意識化していく。そうすることで,児童自身に国語科説明文教材ではどんな学び方が必要なのか,自分にどんな学び方がついてきたのかを知らせる。特に,過程の学力のイ(思考・学び方)に視点を当て指導にあたった。
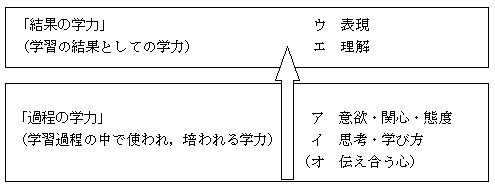
(2) 目標に対する到達度をつかむための評価方法
時間ごとに評価規準を具体的な子どもの姿でとらえ,実現可能な評価方法を工夫する。評価項目については精選し,学年内・学年間で共通理解を図っておく。また,単元の最初における児童の実態のとらえ方や,単元の終末での評価の方法,補充的な学習や発展的な学習については,今後,更に検討していきたい。
▼国語科単元セット
(1) ねらい
○ 単元における基礎・基本を洗い出し,ねらいを明確にした授業をする。
国語科は,教科書を教えるのではなく教科書を使って言葉の力をつける教科で
ある。したがって,教師がねらいをどこにおくかで指導も変わり,子どもの姿も
変わってくる。そこで,この時期にこの教材でどんな力をつければよいのかを
明確にしたbカード(単元の基礎・基本)を作成し,共通理解して進められるように
する。
○ 読み方・書き方・聞き方・話し方を洗い出し,子どもの力としてつける。
子どもに活動を通して,「~方(かた)」を身に付けることができるようにするために,
学習過程のどこでどんな指導をするかを明確にしたcカード(単元の学習計画・
評価規準・育てる過程の学力)を作成する。教師が意図的に活動を組織する
ことで,自分の力で読むこと・書くこと・聞くこと・話すことのできる子が育つと考える。
○ 評価の方法を洗い出し,指導に生かす。 思考や感覚を伴う,見えにくい学力を
どのようにして評価すればよいのか,評価の方法を開発する。
(2) 作成の手順
○ 学習指導要領を読み,その学年での目標と指導内容をつかむ。
○ 教材文を読み,教材の特徴・価値をつかむ。
○ 児童の実態をつかむ。・・・そのテスト・方法の開発
○ 学力をつけるための指導の工夫(ポイント)を明らかにし,学習計画を立てる。
・ 読みと表現の関連をどう図るか。
・ どんな活動を通して,どんな力(読み方・書き方・話し方・聞き方・言葉の力)を
つけるか。
・ 子どもの意識の流れや意欲の持続のための工夫はどうするか。
・ どこでどんな学び方をつけるか。(cカード育てる過程の学力に表現)
・ 少人数授業をどうするか。
|