| 2002-2004年度 学力向上フロンティア事業研究紀要 教科学習の見直しと評価の改善 |
| 9節 研究の成果と課題 ▼教科学習の見直し (1) 算数科・国語科で育成する学力と評価規準 (2) 基礎・基本の定着と補充的・発展的な学習 【単元セットの作成と活用】 ○ 単元セットを作成することで,単元ごとに全時間の学習活動を構想し,その活動に 沿って児童の具体の姿を想定して,A(十分満足できる状況)とB(おおむね満足 できる状況)を判断するポイントを作成することができた。 ○ 評価規準が明確になったことで,基礎・基本をおさえB評価に到達させるため の,個に応じた支援を考慮した教材・教具やワークシートづくりができた。 ○ 毎時間の育てる「過程の学力」の重点を明確にしたことで,算数科の学び方を いつ,どのような観点で評価し,育てるかが共通理解でき,授業中の指導と評価に 生かすことができた。 ○ ファイル化することで,教師が教科の基礎・基本や育てたい力・評価内容等を 共有化でき,互いに情報交換しやすくなった。少人数等の打ち合わせ時間の 不足を補う役目も担っている。 ○ eカードの指導項目の中で,80%に達していないものには△を入れ,次年度に 申し送ることで,次年度の指導の改善に生かしている。 ○ 習熟度別コース学習においての交流学習が子どもの学びの意欲や目的意識を もたせるために有効であることが分かった。 ● その教材(単元)の本質に視点を当てた場合,単元ごとに観点別評価の軽重が 違っているが,学期や年間を通して,再度4観点の評価のバランスを見直す必要 がある。 【補充的・発展的な学習】 ○ 補充的な学習と発展的な学習の本校における考え方をまとめ,それをもとに 補充的な学習や発展的な学習の教材づくりに取り組み始めることができた。 ▼評価の改善 (1) 過程の学力と評価 【過程の学力と評価】 ○ 3年間の子どもへの意識調査の結果(次のグラフ),過程の学力についての 質問に対して,「かなりできる」「できる」の割合が増えている。このことから, dカードの活用により,算数科ではどんな学び方をすればよいかが分かり, 子どもの学び方への意識が高まってきたととらえる。 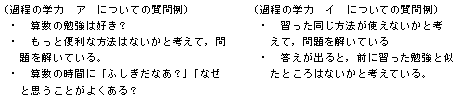 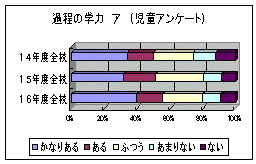 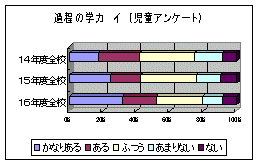 ○ 国語科説明文教材で育てる学び方を子どもとともに見つけ,整理し,意識づけて いくことで,学び方が分かり,子どもに自ら学んでいこうとする姿勢が育ってきた。 ● 本校における数学的な考え方のとらえは明確になったが,児童の実態や指導者 の授業の進め方のちがいから,クラス間でのポイント数に差異があるので,学年団 の共通理解を一層進めていく必要がある。 ● dカードは,児童の自己申請によりポイント化されているため,評定に生かす際の 信憑性に欠ける面がある。しかし,ポイントの累積結果には個々の児童の傾向が 現れてきているので,今後も評価と指導を積み上げることにより,児童の自己 評価力と教師の評価力を伸ばし,客観性の高いものにしていかなければならない。 (2) 結果の学力と評価 【結果の学力と評価】 ○ 全員の子ども一人一人を確実に見取る机間指導(丸付けによる評価と支援)で, B評価に達していない子への支援をその場で行うことができ,その時間の 評価規準(B評価)への達成率を高められた。子どもにとっても,自分のしたことや 考え方に即座に評価がなされ,指導や賞賛が受けられるので,次への意欲や 自信につながった。 ○ eカードを活用することで,個々の子どものB評価到達の状況を,教師・子ども・ 保護者の3者が共有することができ,その後の指導に役立てることができた。 特に,単元途中で実施する場合,観点ごとの実現状況を把握することで,その 観点の補充的な学習や発展的な学習の内容やねらいが明らかになり,個に応じた 支援に有効に生かすことができた。 ● 単元の終末に行ったeカードでは,どの観点でも80%達成者が80〜90%に達して いるにもかかわらず,その後に行った県版テストでは,80%に満たない 観点(例:下グラフ)があった。評価テストの内容をさらに検討するとともに,定着に 向けての繰り返し学習のあり方を工夫したい。 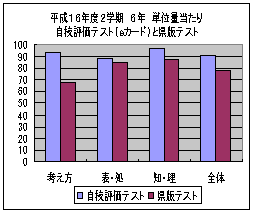 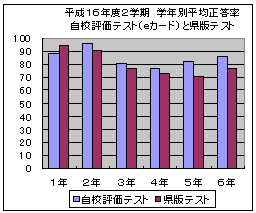 |